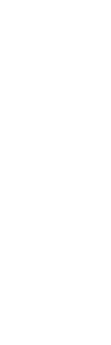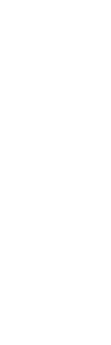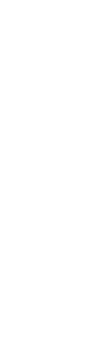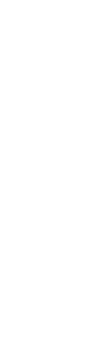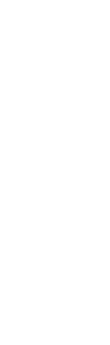ブログ

10年なんて月日はあっという間だ。
それでも10年でいろんなことが変わっていく。
大輔は有希乃が店を出したのを人伝に聞いた。
夢を叶えた有希乃に会いたかったけど、どの面を見せていいのかわからなくて躊躇していた。
15年前、大輔と有希乃は付き合っていた。食品会社に勤める大輔と料理好きな有希乃は気が合った。デートは専ら食べ歩き。
イタリアン、フレンチ、焼肉に居酒屋。中華も行ったし山奥の蕎麦屋にも行った。有希乃がとりわけ好きだったのが寿司だった。
高級店には滅多に行けなかったけど給料のほとんどを食べ物に使っていたと思う。
ある時、有希乃が言った。
「私、お店やりたいな」
「店って、飲食店?」
「そうだよ」
「有希乃がやるなら、洒落たカフェみたいなの?」
「ううん、お寿司屋さんやりたい」
大輔はびっくりして思わず吹き出してしまった。
女の子が寿司屋をやるなんて無理に決まっている。修行は大変だし、なにせ男社会だ。女性なんて受け入れてくれるわけがない。
有希乃がおもむろに取り出したのは寿司の学校のパンフレットだった。数十万で数ヶ月、寿司のことを学んで就職も斡旋してくれるという。
「面白そうじゃない?」
「まぁ、そうだけど、本気なの?」
こうと決めたらすぐ行動するのが有希乃の性格だった。半年間のカリキュラムを終え、寿司屋で働き始めた。休みも違うしお金を貯めるからと大輔の誘いにもあまり乗らなくなって、合うこともなくなった。メールもいつしか途切れ途切れになった。
大輔も新しい彼女を作ろうとしたが、なかなかそうはいかない。有希乃と一緒だった頃をよく思い出すようになっていた。
有希乃が働く姿を見たい。有希乃が握る寿司を食べてみたい。そう思いながら行動に移せなかった。
夏がそろそろ終わりを告げようとする時、思い切って有希乃の店に行く事にした。客としてじゃない、昔の友人として、夢が叶ったお祝いを言いたかった。
日本酒を手土産に店の前に立つ。目立った看板もなく、小さなお品書きが玄関の前にあった。扉を開けようとしたが鍵がかかっていた。女1人で仕事してるんだから当然かもしれない。磨りガラスの切れ目から覗くと仕込みをしている有希乃の姿が見えた。
扉を叩くと有希乃が気づいて、店の中に入れてくれた。
「久しぶりじゃない。元気?」
「おめでとう」
「何年経ってると思ってんの?」
有希乃が笑った。長かった髪はばっさり切られていて帽子の裾から刈り上げられたうなじが見えた。
お祝いの酒を渡すと有希乃は軽くお礼を言った。
「お寿司食べる?昨日の残りのネタだけど」
断る理由もなかったから大輔はカウンターに座った。
カウンターと奥の厨房の仕切りに暖簾がかかっていて薄い藍色に白地で「ゆき乃」と染め抜かれている。有希乃の好きな藍色だ。
有希乃は小気味よく握った。
白身に赤身、イカにウニ。
なんとなく男の職人が握った寿司とはちょっと違う感じがした。
コハダが出てきた。
頬張って飲み込むと大輔は思わず頷いた。塩も酢も実にいい塩梅だ。久しぶりに美味いコハダを食べた気がする。
コハダは漢字で「小肌」とも書く。
いかにも女性っぽいネタではないか。
大輔はまた有希乃とやり直したくなった。
「あれ、もうお腹いっぱい?」
「俺、店、手伝おうか?」
「ダメ、ウチのスタッフは女性オンリーなの」
有希乃は悪戯っぽく笑った。

2018年2月14日
ふらっと京都に行った時のこと。
武大は無性に寿司が食べたくなり店を探した。
京都の夏は茹だるように暑い。祇園辺りを散策して、高台寺のアップダウンの激しい坂を歩き汗が噴き出す。
ふと見ると、江戸前寿司と書いた看板を見つけた。京都で江戸前寿司って珍しい、入ってみることにする。
カウンターとテーブルだけのこじんまりした店だった。60を過ぎたぐらいの大将がひとりで切り盛りしていた。とりあえず生ビールを頼む。だが、瓶ビールしかないという。まぁ、しょうがない。瓶ビールで我慢してグラスに注ぎ一気に飲み干した。噴き出していた汗が一気に引いていく気がした。
つまみをお任せで頼んだ。京都らしく、湯葉の刺身が出て、蛸の柔か煮が続いた。可もなく不可もなく無難な味だった。武大は気になる物があった。カウンターの上に置いてある玉子焼きだった。まだ開店間もない感じだったので、おそらく焼きたてだろう。大将に玉子焼きを切ってくれと頼んだ。
口にして驚いた、卵の味が濃く出汁も効いている。湯葉や蛸より玉子焼きのが気に入った。
「大将、美味い玉子焼きですねぇ」
「おおきに。やっと玉子焼きを褒められるようになりましたわ」
意味がよくわからない。60も過ぎているのだからきっとキャリアは40年は経っているはずだ。キョトンとしている武大に大将はつとつと話始めた。
元々は関東の人間で、東京で修行中に京都出身の女性と出会い結婚して、ここに店を構えたという。2人で店を切り盛りしてたらしいが、博打好きが興じて、仕込みを女将さんに任せるようになった。仕入れをして自分はパチンコや競馬に出かける。夕方に店に戻り女将さんが仕込んだネタを握る。手先が器用な人で大抵の仕込みは直ぐ覚えたという。
女将さんの大の得意は玉子焼きだった。お馴染みさんにも好評でいつしか大将は玉子焼きは一切焼かなくなったらしい。
「アホやったんですよ。女房の体調が悪いのも気づかず遊んでたんやから」
女将さんは癌だった。しかも末期の膵臓癌で闘病生活も長くなく亡くなったという。
女将を亡くした後、博打は一切辞めて仕事に打ち込んだ。元々は腕のいい人だったのだろう。お馴染みさんも徐々に戻ってきて店もなんとか持ち直した。
「でも、玉子焼きだけはお馴染みさんに褒められへんかった」
大将が恥ずかしそうに笑う。
「いや、これなら天国の女将さんも納得じゃないですかね。ま、ボクは女将さんの玉子焼き食べたことないけど。食べてみたかったな」
大将にビールを勧めたが、酒も博打も足を洗ったからと断られた。
「息子2人は勤め人になったけど、孫が、じいちゃんみたいな寿司屋になるんやって言うてくれてな。それまでは頑張らないかんと思って」
そう言って大将は笑った。
人生はやり直しがきく。武大はそんな言葉を思い出した。
そして、玉子焼きをお代わりした。

2017年10月20日
「お父さん、入院したよ」妹の貴和子からメールがきた。父の博は癌を患い3度目の入院だ。もしかしたら、今度はヤバイかもしれない。
父の反対を押し切り、東京の大学に進み、念願だった広告代理店にも就職した。もう直ぐ40歳になるのだが結婚はせず、仕事一本で生きてきた。
もしかしたら、博の血を引いているのかもしれない。父の博は小さな寿司屋を営んでいた。地元ではそれなりに名の通った寿司屋で田舎に似せないいいネタを置いてあると評判だった。ネタを吟味して手を加えた仕込みをする江戸前の握りだった。博が特に力を入れていたのは鮪の仕入れだ。その時季の1番いい鮪を仕入れるのが博の流儀だった。
いい鮪を仕入れると、そんな日の博は上機嫌で学校から帰ると鮪をブロックに捌きながら
「腹減ってないか」
と、聞いてくる。真紀子は何を食べさせてくれるのか知っていた。皮ぎしの身をスプーンですくい手巻きにしてくれる。トロに目がない真紀子の大好物だった。海苔の香りと鮪の脂がたまらない。子供がてらにこんなものを食べて贅沢だと思ったけど、これも寿司屋の娘の特権だと思っていた。
家を出てからはそんな事もなくなった。家を出たのと同時に寿司屋の娘の特権も失ったのだ。10年前に母の須磨子が他界し、1人で店を切り盛りしていた父親だったが癌を患ってから廃業していた。
社会人になり、それなりの給料を貰うようになって寿司屋に出入りもするようになったけど、父の巻いてくれたトロの手巻き以上に美味しいトロ鉄火に遭遇した事がなかった。
妹の貴和子に今週末、帰るとメールを返信して、クライアントとの打ち合わせを終えた帰り道、一軒の寿司屋を見つけた。
カウンターに座り、生ビールを頼んだ。真紀子より一回りぐらい歳上の大将に今日のおすすめを聞いた。
「今日はねぇ、塩釜からいい鮪が入ってるよ」
そう言って、嬉しそうに大将は冷蔵庫から鮪のブロックを取り出した。昔、父親の博もこんな風に嬉しそうに真紀子に見せてくれたものだ。まだ、掃除のしていない鮪のブロック。皮もまだ付いていた。もしかしたら、あの頃の皮ぎしの手巻きが食べられるかもしれない。
「大将、無理なお願いをしてもいいですか?その鮪の皮ぎしで手巻きを巻いて欲しいんです」
「お、旨いところ知ってんだねぇ。いいよ、お姉さん、べっぴんだしサービスしたげるよ」
大将はそう言って鮪を捌き出した。そして、皮ぎしの身をスプーンですくっている。真紀子の手にトロの手巻きが手渡された。
海苔の香りが鼻腔を擽る。頬張ると鮪の柔らかい脂の旨みが口の中に広がった。
あぁ、この味だ。子供の頃、お父さんが巻いてくれた手巻きの味。涙が出てきた。昔の思い出と一緒に。
「あ、ごめん、わさび入れすぎたかな」
真紀子は涙を拭きながら首を横に振った。

2017年6月22日
晃平はスマートフォンの地図アプリを頼りに香苗の部屋に辿り着いた。
インターホンを鳴らしたのだが、それに反応することもなくドアが開く。
おそらく、約束の時間とぴったりだったから、晃平だと思ったのだろう。
暫く振りに会う香苗は化粧っ気もなく、長い髪を束ねていた。別居して4年、一緒に暮らしていた頃はもう少し短い髪だったと思う。それよりも、マニュキュアもしなかった指先には少しデコレーションされたネイルアートが施されていて驚いた。
「離婚届。サインと印鑑頼む」
このまま、別居のままでもよかったけど、踏ん切ることにした。子供2人はもう社会人。離婚になんら支障はない。まぁ、せいぜい子供たちの結婚の時に少し面倒かもしれないが、晃平も香苗もまだ50過ぎて間もない。新しいパートナーを見つけて第2の人生を歩むにはまだ充分な時間があると思ったからだ。離婚の話を切り出したら、香苗はあっさり承諾した。もしかしたら彼女もそれを早々に望んでいたのかもしれない。
「もし、なんかあったら連絡してくれ」
「なんかあったら?私たち、離婚するのよ。他人同士、連絡する必要なんて、ないんじゃない?」
少し、妙な笑顔で香苗は言った。昔から、キツイことを笑って言う女だった。
いや、違う。付き合ってた頃はそんなことはなかったと思う。一緒に暮らしだして、子供が産まれ、日々の生活の中でお互いの価値観が違うことに気がつき始め、彼女はそんな風になったのだと思う。
悪いのは俺なのかもしれない。晃平はふとそう思った。
「じゃあ」
と、声をかけて香苗のマンションを後にした。呆気ない幕切れだ。気付けば腹が減っていた。そういえば午前中にクライアントとの打ち合わせが長引いて昼飯を食べるタイミングを逃していた。香苗との約束もあったし、時間に遅れた時の香苗の眉間に皺を寄せた顔を見るのが嫌だったし。
この街は来たことがないわけじゃないが、知ってる店もなかった。晃平は知らない街で寿司屋に入るのが密かな楽しみだった。便利な世の中になった。スマートフォンを取り出し、近くの寿司屋を検索する。歩いて10分ほど、駅からは逆方向だが良さそうな寿司屋を見つけた。
店内に入る。カウンターとテーブルだけの小さな寿司屋だった。色黒で背の小さな大将がカウンターかテーブルにするか聞いてきた。普段ならカウンターに座るところだが、テーブルに座ることにした。
瓶ビールを頼み、先ずは一気にコップ一杯を飲み干した。そういえば香苗と出会った頃は時々、寿司屋に行ったのを思い出した。まだ20歳そこそこだった2人は薄給で、それでも背伸びして回らない寿司屋に行った。なんだか大人になった気がしたものだ。
やがて、香苗が身籠り、結婚することになった。晃平は香苗に精一杯の指輪をプレゼントしようと当時の蓄えをほとんど使い果たした。
「もう贅沢はできないね。最後にお寿司食べに行こうか」
2人で入った古い寿司屋。60過ぎの夫婦で切り盛りする小さな寿司屋だった。
「並寿司にしよ。お金無いしさ」
2人で食べた並寿司を思い出した。
瓶ビールを飲み干し、色黒で背の小さな大将に並寿司を注文した。一瞬、怪訝そうな顔をされたが、すぐに黒い桶に盛られた並寿司が運ばれてきた。マグロ、イカ、エビ、タマゴ、タコ、アナゴ、鉄火巻、カッパ巻き。ビニールでできた人造ハランが添えてあった。並寿司なんて食べるのはあれ以来だと思う。今では少しは稼げるようになり、名の知れた寿司屋にも行けるようになった。それでも、今食べている並寿司がやけに美味しく感じた。
「大将、ご馳走様。お釣りは要らないから」
店を出た。並寿司。並ってなんだろう。離婚したら並の人生じゃ無くなるのだろうか。夕暮れの新緑の風を感じながら、晃平はそんなことを考えていた。

(フィクションです(笑)若大将が書いたショートストーリーの8作目になります。カテゴリーで以前の作品をご覧いただけます。ご興味のある方、どうぞ)
2017年4月24日
祥子にはどうしても好きになれない食べ物があった。
うにだ。
子供の頃、父親に連れて行ってもらった回転寿司。
「旨いぞ」
と、言って勧められ口に運んでびっくりした。
薬くさいような消毒薬のような微妙な味。
子供心に大人はこんなものを好むのかと驚いた。
以来、口にしたことはない。
あれから10数年が過ぎ祥子も自分のお金ですし屋に入れるようになった。
まぁ、回転寿司ではあるが。
近頃では回転寿司もレベルが上がって立ちのすし屋と遜色ないねたも
ふんだんにある。
でもうにだけは食べようとは思わない。
あの、消毒のような記憶が甦るのだ。
一生、縁がないと思っていた
そんな祥子にもいい男友達ができた。
元という北海道出身の彼だ。
ガソリンスタンドのアルバイトで知り合った。
無骨な大人しい男だった。
2人とも映画が好きでそんなとこが引き合ったんだと思う。
都会育ちの女と田舎育ちの男。
人生はいつもひょんなことから始まる。
ある日、両親の話になった。
祥子のところは典型的なサラリーマンだったが
元の実家は水産加工会社を経営していた。
いずれは実家を継ぐという。
「へぇ、じゃあいつか北海道に帰るんだね」
祥子はちょっと寂しくなったが
知り合ってまだ3ヶ月。付き合ってるのかさえはっきりしてないのに
がっかりしてる自分に少し驚いた。
「うにの加工してるんだ。大変だけど結構実入りは良いみたい」
「うに?うにってあのうに?」
「そう、すしとかにするやつ」
「無理、無理、無理!あたし、うにだいっ嫌いなの!」
「え、あんなに旨いのに何で?」
祥子は子供の頃の話をした。
元がケラケラ笑う。
「知らないんだよ、本物の旨さを」
いつかすし屋に行こうという話になった。
バイト代も出てすし屋に行くことになった。
祥子はあまり気が進まなかったが元はノリノリだ。
「久しぶりだもん、すし」
すし屋のガイドブックでこの店ならという店を元が選んできた。
高級そうだったがネタの値段が全て明記してあり安心して
食べられそうな店だった。
「いらっしゃい」
まだ30過ぎぐらいの若い大将だった。
飲めない2人はあがりを頼んで早速握ってもらうことにした。
マグロ、中トロ、白身。
玉子に穴子。
突然、元がうにの話をし始めた。
実家がうにの加工会社だということ。
そして祥子のうに嫌いなこと。
若い大将は笑って言った。
「その薬くさいのは防腐剤の香り。輸入物や粗悪なものには
たっぷりふりかけてある。上物は薬の味なんかしないよ」
そしてうにが出てきた。

祥子はたじろいだが元も強く言うので思い切って口に入れた。
驚いた。
あの嫌な味は全くなく柔らかな甘みと風味が徐々に広がる。
目からうろこだった。
「な、旨いだろ?これがうにの味だって。ねぇ大将」
祥子はこれで北海道にもいけるかな、と思った。
すし屋のカウンターには発見がある。
一宮 すし 寿司 すし券 でら吟 宴会 接待 法事 慶事 結納 ランチ ワイン 記念日 誕生日 出前
2012年7月25日
修平はなんとなく入った飲み屋で驚いた。
何年ぶりだろう。奈美子と再会したのだ。
彼女とは10年ちょっと前しばらく付き合っていた。
行きつけの店の人気ホステスだった。
向こうも驚いた表情だったけれどすぐに懐かしい笑顔に変わった。
結婚してその世界とはおさらば。
しばらくはメールとかもしていたけれどいつの間にか
連絡が取れなくなっていた。
水割りで乾杯。
「久しぶりね。元気だった?」
グラスを静かに鳴らす。
「驚いた。幸せに暮らしてると思ってたけど」
「離婚したの。私は結婚にむいてない」
肩をすくめて笑う。10年前となんら変わっていない仕草だ。
少し戸惑いながら飲んでいた。
その日は新しい携帯の番号を交換して店を出た。
3日後、修平の携帯が鳴った。奈美子からだった。
「驚いた?ご飯でも食べようよ。久しぶりに」
女はよくわからない。
修平は45年生きてきて今だ女心の理解が出来ない。
でも、断る理由もないので週末に約束を入れた。
待ち合わせの場所で修平は驚く。
あの頃となんら変わらない美菜子の姿があった。
この間は夜の店だったし気づかなかったが
奈美子は修平より二つ年上。
もう50歳にも近いはずだがとてもそうには見えない。
どう見てもまだ30代の肌艶だ。
「どこ行こうか?」
「ねぇ、あそこのすし屋にいこ。大将元気かな?」
奈美子に言われて思い出した。
そういえば別れてからほとんど顔を出していない。
久しぶりに悪くないと修平は思った。
店に入ると大将は一瞬驚いた顔を見せたが
何もなかったようにあの頃の顔に戻った。
さすが、職人だ。
ビールで乾杯して玉子焼きをつまむ。
「あの頃と変わらないな」
「私?変わったわよ、かなり」
「そうには見えない」
「色々あったのよ」
「そうなんだ」
それ以上聞くのはよした。
「あなたは?まだ奥さんと一緒にいるの?」
「あぁ」
「あなたは何にも変わってない」
そう言ってケラケラ笑う。
女房と別れて奈美子と一緒になろうとも思ったが
踏ん切りがつかなかったのが別れた理由だった。
「そうだ、大将、穴子、穴子を握って」
奈美子が突然言い出す。
修平は思い出した。ここの穴子が絶品だったことを。

「んー、美味しい。やっぱり大将の穴子が好き。
大将の穴子も全然変わってない」
奈美子はそう言って首をすくめた。
奈美子がこの街に帰ってきたのは
この店の穴子を食べたかったのか
それとも修平とやり直したっかたのかは定かではない。
偶然か必然なのか。
修平は穴子を焼いた香ばしい香りの中で
ぼんやり考えていた。
すし屋のカウンターには変わらない何かがある。
一宮 寿司 すし券 でら吟 宴会 接待 法事 慶事 結納 記念日 誕生日 ワイン 弁当 出前 ランチ
2012年6月28日
就職して1ヵ月が経った。
誇りっぽい倉庫で幸司は先輩の早河と作業をしていた。
「仕事慣れたか?」
「いえ、まだまだです」
「酒、飲めるのか?」
「少しなら」
「付き合え」
「あ、はい」
上司に言いつけられた倉庫の片づけを早々と済ませ
早河が行きつけの居酒屋。焼き鳥の煙が充満していた。
「お前の実家は何してんだ?」
「すし屋です。でも親父は死んで兄貴が継いでます」
「へぇ、すし屋か。旨いもん食って育ったな」
早河がジョッキを傾けながら呟く。
幸司には嫌味に聞こえたが、切り返す。
「俺の親父は漁師してんだ。いまだに。しかも鰹の一本釣りだ」
「へえ、漁師ですか?先輩こそ旨いもん食ってるじゃないですか」
早河は無表情で鼻で笑って
「お前ほどじゃねぇよ」
と応えた。
それから2人はいい飲み友達になった。
漁師とすし屋。気があったような、兄弟のような。
不思議な感覚だった。
ある日のこと、いつもの居酒屋に鰹の刺身が並んだ。
「先輩、鰹ありますよ」
「いや、この鰹は旨くねぇ。大きさ、身の色でだいたいわかる」
「そうなんですか。さすがですね」
「ところでお前、鰹の握り、食ったことあるか?」
幸司は親父にも兄貴にも握ってもらったことがなかった。
「うめぇんだぞ。脂があっても無くても、鮮度がよければ最高だ」
早河の故郷ではぶつ切りに切った鰹で作る「てこね寿し」
という郷土料理があるという。
「でもな、握りが旨いんだ握りが。兄貴に教えてあげな」
久しぶりに兄貴の声を聞いた。
「兄貴、鰹握ったことあるか?」
「鰹?鰹は握ったことねぇぞ」
幸司は早河のことを話した。
「そうか、なら一度仕入れてみるか」
幸司は就職して初めて実家に帰った。
「鰹、仕入れてみたぞ」
「で、どう?」
「まぁ、食ってみな」

頬張ると、マグロとはまた違う風味が広がる。
生姜と浅葱の香りが鼻腔をくすぐる。
「兄貴、旨いよ。臭みもないし」
「ただ、目利きが難しい。何本も駄目にしたよ」
これなら早河も喜んでくれるかも知れない。
よし、早河に食ってもらおう。
合格が出るかどうかわからないが
ふだん世話になっている早河にどうしても喜んでもらいたかった。
次の休みに早河を誘った。
鰹を食べた早河は旨いとも不味いとも言わなかったけれど
食べてくれたことが嬉しかった。
早河は幸司の兄にビールを勧めながら
「いい弟さんですよ」
と、似合わないおべんちゃらをいっていたが
まんざらでもなさそうだった。
今度は秋だ。今度は脂の乗った鰹で
早河に旨いといってもらおうと思った。
すし屋のカウンターには思い出の味がある。
一宮 寿司 すし券 でら吟 宴会 接待 法事 慶事 記念日 誕生日 個室 弁当 出前 ワイン ランチ
2012年5月30日
臨月はもう来月に迫っていた。
美和子は母親の里子の顔を見たくて帰省しようと思った。
父親には反対された結婚だった。
彼が中卒の塗装屋でバツイチ。若気の至りだったと
里子が説得をしたが父の真之は納得しなかった。
それでも美和子のお腹の中には小さな命が宿っていたし
ペンキにまみれて働く彼の傍に何より居たかった。
結局、式も披露宴もない寂しい結婚になってしまった。
それでも美和子は幸せだった。
お腹の赤ちゃんの成長と夕飯を用意して彼の帰宅を待つ。
そんな毎日が幸せだったのだ。
それでも出産間際にどうしても一番の理解者である里子に
自分が産まれたときの話を聞きたくなったのがその理由だ。
「ただいま」
久しぶりに帰った実家はがらんとしていた。
出迎えたのは真之だった。里子は外出中だった。
「おう」
と、そっけなく応える。まだ納得はしてないのであろう。
居間に入ってテレビのスイッチをつけた。
「父さん、お茶でも入れようか?」
美和子は精一杯、平静を装った。
「いや、いい。美和子、腹へってないか?
寿司でも食いに行くか?」
予想だにしなかった真之の言葉に驚いたが小さく頷いた。
近所の真之の行きつけのすし屋だった。
美和子も子供の頃はよく付いて行ったものだ。
でもここ10年ぐらいはほとんど行っていない。
久しぶりの訪問だった。
「いらっしゃい!あれ?美和ちゃん?
綺麗になったねぇ。あ、結婚したんだって?
赤ちゃんまだかい?」
立て続けに大将は続ける。
すると、女将さんが大将の頭をはたく。
「ちょっと、あんた!」
「あ、しまった」
首をすくめる大将を見て美和子は真之がまだ納得してないのを悟った。
ビールを飲みながら玉子をつまむ真之。
取り立てて話すこともなく好きなものを食え、と言う。
テレビには昼のバラエティ番組が流れていた。
窓の外にはもうすぐ満開の桜の木々が見える。
子供の頃よく遊んだ公園だった。
「大将、そろそろ鯛はどうだ?」
「谷口さん、だいぶ脂ものってきましたよ。
卵(こ)もたっぷり腹んでるし」
「こいつに握ってやってくれ」

実に美しい握りだった。
真之が話しはじめた。
「美和子、鯛はな、産卵間際になると体力つけるために
餌をたらふく食って肥えるんだ。美味いぞ。
お前もたらふく食って元気な子を産め」
それまで黙っていた真之が発した言葉に美和子は驚いた。
「美味しい。ありがと。父さん」
そして新緑の頃に元気な女の子が産まれた。
美和子はその娘に
「桜子」
と名づけることにした。
すし屋のカウンターには、親子の愛がある。
一宮 寿司 すし券 でら吟 宴会 接待 法事 慶事 歓送迎会 結納 記念日 誕生日 出前 弁当 ランチ
2012年4月25日
太一がこの街に出て5年が過ぎようとしていた。
田舎の街に不満があったわけではない。
なんとなく都会に憧れただけだ。
大学受験には失敗したが専門学校に進学した。
太一の父、徳三は小さなすし屋を営んでいる。
田舎の街で本格的な江戸前寿司を食べさせてくれる店で
特別流行っていたわけではなかったが根強いファンも多く
太一の学費と仕送りぐらいは稼げていた。
周りからはすし屋を継がないのか?とよく言われた。
寿司は好きだったし、徳三のことを嫌っていたわけでない。
ただ本当に都会に憧れただけだ。
専門学校を無事卒業し、旅行会社に就職していた。
仕事に慣れてくるとツアーであちこちの街にいけるのが魅力だった。
楽しみになったのは、その町のすし屋に入ること。
北海道には北海道の。
北陸には北陸の。
それぞれの美味い寿司がある。
寿司を好きになったのは徳三のお陰だと思う。
実家にいるころ、おやつ代わりでよく握ってくれた。
やれ鉄火巻きだのお稲荷さんだの。
いいマグロが入ったときなど脂ののった皮際の身で
ネギトロなんかも巻いてくれた。
それでも太一は徳三に、
「すし屋になれ」
と一度も言われたことはなかった。
なれと言われれば拒む気もなかったが
自分から後を継ぐとも言えなかった。
その日は関西方面への帯同だった。
ツアー客から開放され街に出る。
小さなすし屋に入ることにした。
いつものように特上の握りを注文する。
太一のいつものパターンだ。
値段も安心だしまず間違いないネタが入っている。
関西のすし屋には珍しい江戸前の握りだった。
「美味い」
しっかりした仕事がしてあった。
追加でおすすめを聞いてみる。
太一より一回りぐらい年上の大将は
「今日はいい煮ハマがありますよ」
と勧める。
煮ハマとは驚いた。
江戸前ではこの時季の定番だ。
頬張ると懐かしい味がした。
徳三の煮ハマの味を思い出した。
田舎で江戸前の握りを出している徳三。
何か同じような匂いがした。
大将と色々話をした。
2代目で店を継いだこと。
東京で修行したこと。
亡くなった先代のこと。
なんだか嬉しくなった。
店を出てふと思った。
「俺もすし屋になろうかな」
徳三に言ったらなんていうだろう。
鼻腔にまだ煮蛤の香りが残っていた。
すし屋のカウンターには絆がある。

一宮 寿司 すし券 でら吟 宴会 接待 法事 慶事 歓送迎会 記念日 誕生日 ランチ 個室 出前 弁当
2012年3月28日
博敏はここの時季になるといつも思い出すことがある。
10年前のこと。
菜由佳と付き合って半年ぐらいたっていた。
映画を見に行った。
確か、古いスポ根漫画の実写版。
彼女は興味なさそうだったが博敏が押し切った。
映画の好みや音楽の好みは合わなかったけど
食事と酒の好みだけは相性がいい。
付き合って半年。意見が分かれたことがない。
博敏がカレーがいいといえば菜由佳もそうだったし、
寿司とイタリアンが好きなのも共通していた。
その日は寿司にしようという話になり
映画館の近くの小さなすし屋の暖簾をくぐった。
柔和な笑顔の大将で女将さんも気さくな感じの人。
お世辞にも綺麗な店ではなかったが
2人を温かく迎え入れてくれた。
給料前だったので高いネタは避けようと
入店前に話し合って。
瓶ビールで乾杯。
軽く、つまみを頼む。
玉(ぎょく)にタコぶつ、マグロ。
博敏いわく、すし屋のつまみ「三種の神器」だ。
ビールを2本飲んで冷酒に切り替えようと思ったが
菜由佳が握って欲しいと言うんでそうした。
白身は平目。
イカにコハダにホタテ。
海老に穴子。
〆に牛蒡巻きを頼んだ。
味噌汁を注文したがまだ少し足りなかった。
「私、もう少し食べたいな」
「俺もだ、何にする?」
「同時に言って違ってたらじゃんけん」
悪戯っぽく笑う。
「いいよ、せーの」
「お稲荷!」
2人は思わず噴出した。
「あら、ウマが合うお二人さんね」
女将さんが味噌汁を出しながら笑った。
大将が握ってくれた「お稲荷」は実に美味かった。
頬張ればジューシーで煮汁とシャリがよくあった。
博敏は思った。
男と女の相性なんて容姿とか、身体とかじゃなくて
もっと大事なことがあるような気がした。
お稲荷を食べる菜由佳の横顔が愛おしく思った。
半年後、博敏は菜由佳にプロポーズした。
今では子宝に恵まれ幸せな家庭を築いている。
今日はどこかで稲荷寿司を買って帰ろう。
菜由佳もきっとそんな気分だろうから。
すし屋のカウンターには始まりがある。

一宮 寿司 すし券 でら吟 宴会 接待 法事 慶事 記念日 雛ちらし ふぐ 弁当 ランチ 個室 出前
2012年2月29日
« 前のページ
次のページ »