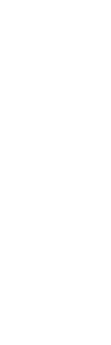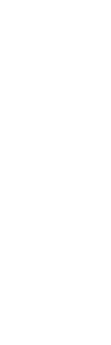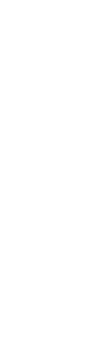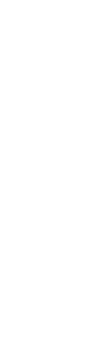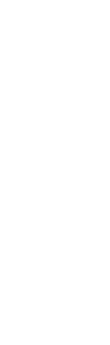ブログ

今年もシンコの季節がやってきた。出始めはまだ数センチ。こんな小さな魚にも鱗も有れば内臓もある。小出刃を使って巧みに捌いていく。すし職人の腕の見せ所だ。
守はため息を吐きながらシンコを捌いていた。早くに亡くなった父の跡を継ぎ、店を切り盛りして15年。魚の目利きも市場では一目おかれるようにもなってきた。今朝のシンコも鮮度が良く、鱗もしっかりとついている。
ため息の理由(わけ)は失恋だった。もうすぐ不惑の歳になるのに未だ独り身だ。10ヶ月、付き合った彼女と別れた。些細なことだったが一度心が離れた女性を元に戻すのは至難の業だということは身に染みてわかっている。まるでシンコの時期のような儚い恋だった。
これで最後にしようと思ったのに。男と女の仲は実に難しい。このシンコを捌くのより遥かに難しい。背鰭を取り、鱗を取り、頭を落として腹を出す。子出刃よりさらに小さなナイフで開いて中骨を取る。濃いめのたて塩に漬け、酢で〆る。大きさによって付け時間を変えて、塩梅をみる。シンコを仕込む工程は身体で覚えてるが、恋愛の工程だけは何度やっても身に付かない。
またため息を吐いた。
まぁ、しょうがない。次だ次。笑い話にしてしまおう。酢で〆たシンコを盆ざるに上げる。
さぁ、今日も営業だ。しけた面をお客に見せるわけにはいかない。
「大将、今年もシンコ入ったって。ブログ読んだからきたよ」
「今年も儚いネタの始まりです」
「儚いってなんだよ、また女に振られたか」
苦笑いで返す。
魚の目利きには自信がるが、女の目利きは本当に難しい。
いや、そうじゃない。自分自身へのの目利きかもだ。
1年経てば、またシンコが出てくる。
そうだ、新しい出逢いもきっとあるはずだ。
守は今年最初のシンコを握って付け台に置いた。

2022年8月25日
部屋に帰るとベッドに倒れ込んだ。
2軒目に誘われたけど、その気になれず断った。
洒落たイタリアン、インスタ映えしそうなカフェ。
悪くはないけど、美沙にはどうもピンとこなかった。
「あぁ、美味しいお寿司が食べたい」
食べることが大好きな美沙を食事に誘う男は多いが、寿司屋をチョイスする輩はほとんどいない。
そんな時、武司をいつも思い出す。
別れてから2、3年は経つのだが、美沙に寿司の美味さを教えたのは武司だった。
回転寿司しか知らない美沙にとって目から鱗の話ばかりだった。
ネタの旬、ガリの由来、どうして寿司屋の湯呑みが大きいのか、江戸前の意味、立ち食いのワケ、寿司の食べ方、助六の話、寿司の歴史。
寿司屋の倅の武司には寿司屋の雑学が詰まっていた。そして何より、美味い寿司屋を見抜くのが素晴らしかった。
酒を頼み、つまみをオーダーする。そして頃合いを見て握りを頼む。おまかせが主体の近頃の店ではなく、昔ながらの寿司屋に行く事が多かった。
決して、美男子ではないけどカウンターで見る武司の横顔は頼もしかった。
ひとりで寿司屋に行けるようにもなったけど、寿司の香りを嗅ぐと武司のことを思い出す。
「あぁ、美味しいお寿司が食べたい」
久しぶりに武司にLINEをしようか迷っていた。女癖の悪い武司にはいつも苛立ちを覚えていたが、寿司を食べるだけならいいだろう。
美沙はスマートフォンに手をかけた。

2021年9月8日
シャワーから上がるとスマートフォンにLINEがきていた。送信先は美沙からだった。別れて2年、いや3年は経ってるだろう。開封してみた。
「久しぶり。元気?お寿司食べに行かない?」
寿司に目がない美沙らしい誘いだった。
でも、今更どうしたんだろう。美沙とはしばらく付き合っていたが武司のだらしなさが原因で別れた。以降、連絡も取っていない。
あの頃は、よく寿司を食いに行った。回転寿司しか知らない美沙にとって回らない寿司屋は知らないことのオンパレード。寿司屋の三男坊に生まれた武司は父親に教えられた寿司の雑学が頭の中に詰まっていた。
ネタの旬、ガリの由来、どうして寿司屋の湯呑みが大きいのか、江戸前の意味、立ち食いのワケ、寿司の食べ方、助六の話、寿司の歴史。
寿司屋になってもよかったのだが、店は長男が継ぐと言ったので普通に大学に行き、勤め人になった。
美沙はそんな話に時には目を丸して、時には感心して寿司を食べていた。好物のネタを食べて静かに微笑む横顔がたまらなく可愛かった。
そういえば、美沙と別れてからあまり寿司屋に行かなくなった。実家にも立ち寄らなくなった。
なぜだろう。
多分、飯の香りを嗅ぐと美沙を思い出すからだった。
未練があるわけじゃない、未だ好きという訳でもない。
また、付き合ってもいいけど、自分のだらしなさでまた同じ事の繰り返しになるだろう。
そろそろ、桜の咲く頃だ。
花見にでも行きながら、今度は何の話をしてやろうか。
そんなことを思いながら、LINEの返信を戸惑っていた。

2021年5月26日
葬儀、初七日を終え、親父の店に立ち寄った。9月だというのにまだまだ残暑は厳しい。
主人を失った店内。
静まり返った中に、まだ親父の残像が残っているような気がする。
まだ、4日前までここで仕事をしていたのだ。
「辰巳寿司」
臈纈染で染められた藍色の暖簾が壁にかかっている。付け場は程よく掃除して整頓されていた。
身体の異変を感じながら、その日の営業を終え片付けをしていたのだろう。
カウンターの前で倒れていたのを洗い物をしていた妹、民子が見つけ、救急車を呼んだ。
意識は戻る事なく、その人生の幕を閉じた。
私がもっと早く気づいていたらと、民子は葬儀の最中、ずっと泣いていたが民子のせいじゃない。
それが親父の生き様だったのだと思う。
高校を卒業して東京の日本料理店で6年働いた。母親の持病が悪化したのを機に故郷に帰りしばらく一緒に働いた。
でも、反りが合わなかった。
寿司職人と和食の板前。似ているようで非なるものだ。些細な事で言い合いになるのが嫌で袂を分けた。
以来、親父は妹と店を切り盛りしていた。
そして、俺は隣町で小さな居酒屋を開いた。
冷蔵庫を開ける。当然、明くる日も店を開けるつもりだったんだろう。ネタ箱には綺麗に寿司ネタが納められていた。
鮪、白身、イカ。
車海老、玉子焼き、穴子。
銀缶の煮汁の中には煮ハマが入っている。
相変わらず、江戸前の仕事だった。
民子が立っていた。
「お兄ちゃん、何してるの?」
「ん?親父の仕事っぷりを見とこうと思ってな」
「私、お父さんとお兄ちゃんが付け場に立ってる風景が大好きだった」
「すまん、俺のわがままで」
何も親父のことを極端に嫌ったわけじゃない。市場で時々顔を合わせることもあったが挨拶ぐらいはちゃんとしていた。
自分の店でも寿司は時々出していた。居酒屋なのに美味い寿司だとお客からも好評だった。
この街から寿司屋が次から次へと消えていって久しい。まともな寿司が食えなくなったと嘆く声も聞いていた。
「民子、通夜と葬儀で参列何人だった?」
「しっかり把握してないけど600人ぐらいだと思う」
ほとんど知らせもしてないのに本当にたくさんの人が送ってくれた。全部が全部親父の握りのファンじゃないだろうけど、これも親父の人柄だろう。
「民子、親父の寿司は美味かったか?」
「うん。日本一美味かったよ」
一緒に働いていた頃の仕込みノートはとってある。親父のことだ、それほど割りを変えていることもないだろう。
この街からまともな寿司屋を消しちゃダメだ。
「民子、1ヶ月後、店を開けるぞ。辰巳寿司の新規オープンだ。後継じゃねぇぞ、あくまでも新規開店だ」
民子がまた、泣き出した。
親父、寿司屋の文化を消さないぜ。力を貸してくれ。
その時、立てかけてあった巻き簾がカタンと倒れた。

2020年10月19日
朝目覚めていつも気にするのは肩と肘。
痛みはないか、無事に上がるか。
異常がない事を確認して、達矢は起き上がる。
小学2年から野球を始め、甲子園を目指した。
残念ながら県大会で敗退したが、全国制覇をした事がある大学から声がかかり神宮でも投げた。
ドラフトの声もあったが漏れ、社会人の門を叩いた。
「アマチュアの星になる」
そう心に誓い、雨の日も風の日も走り、投げ続けた。
都市対抗にも出場したがもう、肩は悲鳴をあげていた。
30歳も過ぎればアマチュアではベテランだ。そろそろ進退も考えねばならない。
でも、達矢はまだできると信じていた。
故障して半年、整形外科やスポーツ診療所、ありとあらゆる所を訪ねた。
お陰で痛みは治り、ブルペンで投球練習ができるまでになった。
幸い、今年は新型インフルエンザの世界的蔓延で各スポーツが軒並み中止に追いやられていた。社会人野球も例外ではなかった。
達矢はチャンスだと思っていた。シーズンの開幕が遅れれば、間に合う。
でも、全盛期の直球には遠く及ばなかった。
自粛要請の解除に合わせて、学生時代、よく通った寿司屋の大将に会いたくなった。
野球好きだった大将は達矢始め、チームメイトにただのような値段で寿司を振る舞い、ビールを飲ませくれた。
久しぶりに店の前に立った。
「すし勢」
という看板は変わってなかったが随分綺麗になっていた。
「大将、お久しぶりです」
「おぉ、大脇くんか、久しぶり。元気だったか?
ってもこんなご時世だ、元気でもないか」
「お陰さまで、なんとか、ビールをください」
瓶ビールを2人で乾杯した。
「もう、何年になる?」
「10年です」
「早いなぁ。俺はお前さんがドラフトにかかるのをホント楽しみにしててな、でも、社会人の結果も見てるよ。頑張ってるじゃねぇか。なに、プロに行くのが全てじゃねーや」
そう、プロには未練はない。あるのはマウンドだ。
玉子をつまみで食べた。あの頃と変わらない甘くて出汁が効いてて。
コハダを握ってもらった。相変わらず締め具合が申し分ない。
社会人になって上司に何軒も連れて行ってもらったが、ここの寿司以上に美味い寿司に出会った事がない。
「大将、お店、改装したんですね」
「5年になるかな。もう俺も若くない。出前と並寿司中心の寿司屋から変わろうと思ってな。今ではいいお客もそれなりに付いて、お前さん達が来てた頃とはちょっと違うんだぜ」
「へぇ、そうなんすか。大将の寿司は昔から美味いからきっと、大丈夫なんすよ」
「人間はな、変化するのを恐れる生きものだ。でもな、思い切って変わってみると新しい何かに出会えるってもんだ」
達矢はハッとした。
達矢のピッチングは速球を中心に力で押すピッチングだった。
全盛期の直球がないなら変化球で勝負してもいいのではないか。
「そうだな、俺だって若ぇ頃みたいにはいかねぇよ。でもな若い奴にはない経験がある。お前さんも、もう一花咲かせたいんなら変わってみるのも悪かねぇぞ。また、マウンドに上がる姿を見たいってもんよ」
ビールは5本目になっていた。
変化と経験。
自信に満ちた大将の言葉と寿司が達矢の背中を押した。

2020年9月2日
暖冬だったとはいえ3月になれば風は春の陽気を運んでくる。
一人息子の受験も終えなんとかひと段落。
一浪して今年は希望校になんとか合格した。
涼子はシングルマザーとしてここまでやってきた。
育児に興味のない夫と別れて、昼も夜も必死で働いた。
独りで頑張ってきたのだ。
だから、自分へのご褒美は自分であげるしかない。
愛車、FIATのスタートキーを押す。
自分へのご褒美はいつも決めている。
寿司を食べる。
そう決めている。
美味い酒があればいいのだが、今日はドライブも兼ねているのでお預け。
海に面した隣町の、気さくな大将がいる店に行くことにした。
窓を開けると潮風の匂いがする。
あぁ、なんて気持ちがいいのだろう。
「潮寿司」
いかにも海辺の街の寿司屋だ。
ランチメニューがないので、昼も比較的空いている。
そこも魅力だった。
「大将、おひさ~~」
「お、涼ちゃん、久しぶり!
今日は、自分へのご褒美かい?」
年に数回しか来ないが付き合いは15年ほどになるだろうか。
昔は電車に乗りたがる息子とバスと電車に乗り継ぎ来たものだ。
「あ、そう。大ちゃん、大学受かったんだ。そりゃ、おめでとう」
「でもさ、これから地獄の学費」
別れた旦那からは養育費は一切もらっていない。
こんな男の世話になるもんかと、涼子の意地だった。
「大将、今日は車だからノンアルね。昼から飲める?一緒に乾杯しよ」
いける口の大将は生ビールを差し出した。
「かんぱーい」
つまみはお任せ。
ここの大将は寿司屋だけじゃなく割烹料理店でも修行しただけのことはあって、料理も美味い。
お通しは青柳の酢味噌。
蛤と筍のお椀が出て、春を感じる。
「大将、美味しい~~。幸せ」
「そりゃ、涼ちゃんだからいつもより気合入れてるから」
切れ長の目に長い髪。顔立ちもいい。涼子は美人だ。
「大将、絶対、口説かれないからね」
2人で笑った。
ふと、昔を思い出した。
玉子ばかり食べたがる息子にトロを食べさせたらえらく気に入って、トロばかり食べたがるようになって閉口したことがある。
その時、大将がネギトロを食べさせてくれて、これで今日のトロはおしまいと息子をなだめてくれた。
「そんな事、あったかなぁ」
絶対覚えてるはずだけど、大将の照れ隠しだろう。
焼物の鱒の塩焼きが運ばれ、蒸物の蕪蒸しが出た。
「そろそろ握ろうか」
大将の握りも秀逸で、ネタも一工夫してある。
それを煮切り醤油で食べさせてくれる。
付け醤油の店しか知らない涼子には新鮮だった。
塩とレモンで食べさせてくれるイカ
昆布締めの平目は柚子胡椒
鮪の赤身
中とろと続いた。
小肌の締め具合もベストだった。
「しかし、涼ちゃんは口が肥えてるねぇ」
夜の仕事を10年ぐらい続けていた頃があった。
寿司好きな涼子を頻繁に同伴してくれる客とよく寿司屋に通った。
「で、その客とデキたの?」
「なにもないわよ~~」
また2人で笑った。
寿司はいい。
人を幸せにしてくれる。
自分への最高のご褒美だ。
潮風の匂いと車のエンジン音。
さて、今度のご褒美はいつになるのかな?
大将に手を振りながら、車のスタートキーを押した。

2020年7月1日
久しぶりに妹の留美と会う事になった。お互い休みが違うので、社会人になってからは、ほとんど会う時間が取れない。いや、取ろうとも思わなかったのだけど。
駅の改札で待ち合わせて歩き出した。よく考えたら、全くのノープラン。少し早いが軽く飲んで食事でもという事になった。
もうすぐ夏至なので、まだ太陽は高い。ふと見ると暖簾がかかった寿司屋を見つけた。
まだ20代と30を過ぎたばかりの女の客が珍しかったのだろう。大将は一瞬戸惑いを見せたが、カウンターにと促された。
生ビールを頼み乾杯する。確か、留美はあまり飲めないはずだ。
「母さん元気?」
「うん、元気にしてるよ。彼方此方、痛いって言ってるけどね」
大学の頃から家を出て、就職は地元近くに帰ってきたが、敢えて一人暮らしをしていた。
「由奈ちゃんは仕事、順調なの?母さん、いつも心配してる」
母の事が嫌いなわけじゃない。一度は故郷を捨てて出てったのだから、家には帰りたくないと思っただけだった。それに大好きだった父も愛猫のタマももう居ない。あの頃の家とは違う気がしていた。
「そういえば、ウチは寿司率高かったよね」
「そうね、父さんがお寿司大好きだったからね。何かあれば、すぐ寿司の出前をとってさ。そういえば、香寿司の大将、元気?」
「去年、お店、閉めちゃった。脳梗塞になったらしくて、お寿司握れなくなったんだって」
「そうなんだ。子供の頃は父さんによく連れてってもらったね」
「私はあんまり行った事ないけど」
無類の寿司好きだった父。正月、誕生日、入学、卒業、クリスマス。いつも寿司があった。でもクリスマスは肉とケーキが食べたかったのが本音だ。
「よく、留美ちゃんと海老の取り合いしたよね」
「そうだったね。由奈ちゃんの海老、欲しくて」
久しぶりに留美の笑顔を見た。久しく会ってなかったし、LINEで6年付き合った彼と別れたと知ってたから。
生ビールからワインに変わっていた。寿司屋にしては珍しいブルゴーニュのピノノワールが置いてあった。
留美はグラスに少しだけ飲んで、残りは1人でボトルを空けた。
最後に少し握ってもらって店を出た。
「由奈ちゃん、そんなに飲んで大丈夫?」
「大丈夫。酒の強さは父さん譲り」
「私は飲めない母さんの血を引いた」
空を見上げたら、まだ明るい。西の空が茜色だった。
「ところで留美ちゃん、なんで海老が好きだったの?」
「なんでだろ。味が特別好きなわけじゃなし、多分、色が赤いから。女の子の色じゃん」
「えー、それだけ?」
なんだか、笑えた。学生時代は不登校だった妹とこうして一緒に寿司を食べて酒を飲めた。
もしかしたら、いろんな出来事って時が解決してくれるのかもしれない。
海老の寿司を横取りした時の留美の笑顔と今日の笑顔は同じような気がした。

2020年3月7日
挙式を3日後に控えた夜、花嫁になる娘、美沙から寿司を食べに行こうと誘われた。泰造は少し驚いたが娘として一緒に寿司を食えるのもこれが最後だと思い即決した。
通い慣れたいつもの寿司屋。この家に越してきて20年以上になる。それ以来の付き合いだ。暖簾をくぐると、いつもの親父の顔がある。
「いらっしゃい!あれ珍しい、美沙ちゃんも一緒だなんて」
娘が結婚することやんわりと伝えてあったのだが子供の頃から美沙を知る親父も嬉しそうだった。
生ビールで乾杯。つまみをおまかせで頼んだ。蛸の桜煮、鯵のタタキ、鮪のネギ焼。親父のつまみはいつも秀逸だ。
「お父さん、長いことありがとう」
美沙が突然言い出した。
「今更、なんだよ。藪から棒に。なんでもいいから幸せになれ」
考えてみると、泰造の人生にはいつも寿司があった。子供の頃から、そんな裕福な家庭ではなかったが誕生日、進学、正月、節目で食べたのは寿司だった。大人になってもそれは変わらなかった。働き出して、結婚して子供ができても。
「いつもウチにはお寿司があったね」
美沙が海老の握りを頬張りながら言う。
子供達にも、何かあると寿司を食べさせてきた。この店にもその都度、世話になってきた。
「大将、いつもありがとう。ウチの子供たちはここの寿司で育ったようなもんだ」
「何をおっしゃる、いつも贔屓にしてくださって。こうやって嫁に行く前の美沙ちゃんに寿司を握れて、私も寿司屋冥利につきるってもんです」
いつも謙虚なここの親父は数年前に女将を癌で亡くして娘さんと切り盛りしていた。女将さんが生きていたら美沙の結婚をさぞかし喜んでくれただろう。
聞けば、この手の寿司屋が減っているという。回転寿司や持ち帰り専門店に押されているのだろうか。寂しい限りだ。小さな寿司屋には小さな寿司屋の良さがある。アットホームだったり気心が知れたらこんなに落ち着く場所はない。
そんなことを考えていると、親父が握り始めた。
赤身のヅケ、中とろ、平目の昆布締め、コハダに穴子。どれも仕事をしてある江戸前の握りだ。
「大野さん、こんなところでいいですか?」
「ありがとう。最後に牛蒡を手巻きで巻いてくれるかな」
最後に巻物で締めるのが泰造の流儀だった。若い頃、上司に教えてもらった流儀を今も続けている。
勘定を済ませて店を出た。
「お父さんの子供でよかった。だっていっぱいお寿司食べれたんだもん」
式を終えた明くる日、美沙がいなくなってなんだか家の中がガランとしている。いつも家にいた訳でもないのに不思議だ。
「お父さん、どうしたんですか?ぼーっとして」
妻の江美子に聞かれた。
「おい、たまには寿司でも食いに行くか?」
「あら、珍しい、私でいいの?」
「私でってなんだよ。もう、お前しかいないだろう」
今夜はどんなつまみを食わせてくれるだろう。何を握ってくれるだろう。これからもずっと寿司はそこにあるだろう。
誰かの人生と共に。

2018年8月28日
真弘は仕事を終え帰宅し、溜まった郵便物をチェックしていた。東京の大学に行った息子宛ての郵便や、興味の無い健康食品のセールスのハガキの中に大学時代の同窓会の案内があった。
同窓会なんて何年ぶりだろう。中学、高校の同窓会の案内は時折あったが大学の同窓会なんて卒業して以来じゃないかとぼんやり考える。
日付は3ヶ月後の日曜日だった。特に予定もないし、出席することにした。ついでに東京の息子の顔でも見てこようか。
同窓会の会場はキャンパスがあった場所からそう遠くないホテルだった。20数年も経つとすっかり風景が変わっていた。真弘が通っていたキャンパスは移転してもうないし、授業をサボって入り浸っていた喫茶店は小さなビルになっていた。
会場に着くと、男1人と女2人が真弘を見つけて手を振ってきた。
懐かしい顔だ。吉田雄二、荒木仁美、島内百合子。
まだちゃんと名前を覚えていたのに、驚いた。
「安ちゃん、久しぶり!」
少し白髪交じりの髪で吉田が握手を求めてきた。仁美も百合子も続いて手を差し伸べた。
確かに20数年の月日は感じるけど、皆、それぞれあの頃の雰囲気は残っていた。
真弘と3人は一時期、短期のゼミで一緒だった。吉田は2浪してたから歳は2つ上、もうすぐ50歳になるはずだ。
「みんな、変わらないなぁ。俺はちょっと禿げたけど」
真弘は自虐的に言った。
「しょうがないわよ、みんな同じように歳はとるんだから。私だって老眼で眼鏡が手放せない」
仁美が言う。
「私もあの頃より10キロ太ってさ、ただのおばさんよ」
百合子も続く。
久しぶりの再会で昔話に花が咲いた。
あの頃はバブル景気で真弘たち大学生も結構裕福に暮らせた。百合子は日本中央競馬会でアルバイトしてて、下手な日雇いより稼いでいたし、仁美も家庭教師やら塾の講師でなかなかのバイト料を貰っていた。真弘も吉田も親からの仕送りプラスバイト代で新卒のサラリーマンより余裕はあったと思う。
「そういえばさ、覚えてる?月一寿司会」
吉田が思いついたように言いだした。
4人は無類の寿司好きだった。誰が言出屁だったか忘れたけど、月に一度、4人で寿司屋に行こうという会だ。
「覚えてる。覚えてる。百合ちゃん、トロが大好きだったんじゃない?」
百合子は大のトロ好き。吉田は光り物、仁美は玉子、真弘は穴子に目がなかった。
「同窓会の料理、大した事ないしさ、久しぶりの月一寿司会、やらない?」
百合子が言う。
「いいねぇ。今から近くの寿司屋、探そう」
吉田がスマホで検索しはじめた。
歩いて10分ぐらいのところに寿司屋があった。4人が大学生だった頃はまだなかったと思う。暖簾をくぐり、店の中に入る。こじんまりして清潔感のある店だった。大将らしき人にテーブル席があるかと聞いてみた。店の奥の4人掛けのテーブルに通された。
「そうそう、こんな感じの店が多かったね。カウンターは敷居が高いし、4人じゃ話ずらいから」
仁美が周りを見回しながら言った。
瓶ビールを注文して4人で乾杯した。つまみは取らず、大将におまかせで4人前の握りを注文する。
「今でも、みんな寿司は好きなの?」
真弘が切り出した。
「もちろんだよ。田舎に帰って就職したんだけど、東京でそれなりの寿司食べただろ。俺の田舎、いい寿司屋がなくてさ、店を探すのに苦労したよ。でも10年ぐらい前だったかな。出前中心だった寿司屋の息子が東京の寿司屋で修行して帰ってきたんだ。これがなかなかの腕でさ、今はその店に月一ぐらいで通ってるよ」
吉田が鯖の握りを頬張りながらしゃべる。
「今でも月一なんだ。私も今でもお寿司は大好き。お寿司屋さんにお嫁に行きたいぐらいだったもん、適齢期すぎちゃったけど」
仁美が笑って話した。
「私も大好き。だからこんなに太っちゃった」
百合子が首を竦めて言った。
「ゆりっぺは昔からよく食べた」
真弘が穴子を食べながら、ボソッとつぶやく。
「安藤くん、そういうとこ昔と変わんないね」
百合子が軽く睨む。
「でも、不思議だなぁ、俺たち。寿司が好きで集まってさ。それぞれ生き方が違ってて、20年経ってまた寿司でつながった。寿司ってそういう食べ物かもしれないな」
吉田が3本目のビールを注文した。
「ねぇねぇ、せっかく再会したんだからさ、月一寿司会、復活しない?」
仁美が、身を乗り出して言いだした。
「おいおい、みんな遠くに住んでんだから厳しいだろ、月一は」
真弘が遮る。
「安藤くん、そういうとこ、変わってないね」
百合子が言う。
「じゃあさ、4ヶ月に一回でどうだろう。それぞれ幹事になって、みんなの行きつけの店でもいいじゃん。それぞれの街にそれぞれの寿司があるだろうから。4ヶ月に一回、一泊して寿司食うぐらいに余裕はあるだろ」
昔から吉田は話をまとめるのが上手い。
「いいねぇ、それ。私賛成」
百合子が手を上げた。
「私も!安藤くんはどうなの?」
「別に、断る理由はないよ」
「そうそうとこ、昔から変わんないね」
4人で笑った。
人と人、過去と未来を繋げる寿司。
なんて素敵な食べ物なんだろう。
いつまでも、いつまでも、この寿司という文化がずっとずっと繋がっていくのを楽しみにして、4ヶ月を待とうと真弘は思った。

2018年4月24日
今日は一気に暖かい日になりましたね。
太陽が照ってなくてもほんのり暖かい。
もうすぐ春です。
えーと、今日は少し恥ずかしいブログを書きます(笑)
恥ずかしいって言っても、ボクの性癖のことではありません(笑)
実はですね~、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですが時々、ちょっとした小説を書いてます。

毎日、ブログを読んでくださる方なら知っているでしょうが、時々変な文章のそれです(笑)
普段はFacebookにブログをシェアするのですが、小説の時はやりません(笑)
でも、ちょっと読んでもらいたいなぁ、なんて気持ちもあったりします(笑)
寿司をテーマにしたミニストーリー。すべてフィクションです。
きっかけは、毎日書いてるブログに変化が欲しかったからと、自分の気分転換かな。
お時間のある方、よろしければご一読ください。
感想なんぞを聞かせていただけたら幸いです(笑)
小さなすしのストーリー
こちらにまとめてあります。
愛知県すし組合の新聞にも絶賛連載中です(笑)
誰も読んでないと思うけど。
では、次作もお楽しみに(笑)
2018年3月4日
次のページ »