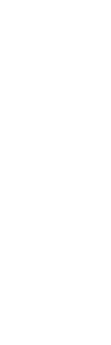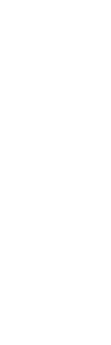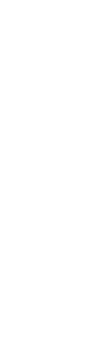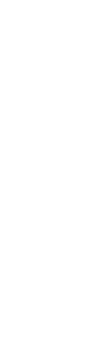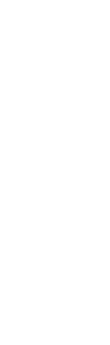トロ鉄火
「お父さん、入院したよ」妹の貴和子からメールがきた。父の博は癌を患い3度目の入院だ。もしかしたら、今度はヤバイかもしれない。
父の反対を押し切り、東京の大学に進み、念願だった広告代理店にも就職した。もう直ぐ40歳になるのだが結婚はせず、仕事一本で生きてきた。
もしかしたら、博の血を引いているのかもしれない。父の博は小さな寿司屋を営んでいた。地元ではそれなりに名の通った寿司屋で田舎に似せないいいネタを置いてあると評判だった。ネタを吟味して手を加えた仕込みをする江戸前の握りだった。博が特に力を入れていたのは鮪の仕入れだ。その時季の1番いい鮪を仕入れるのが博の流儀だった。
いい鮪を仕入れると、そんな日の博は上機嫌で学校から帰ると鮪をブロックに捌きながら
「腹減ってないか」
と、聞いてくる。真紀子は何を食べさせてくれるのか知っていた。皮ぎしの身をスプーンですくい手巻きにしてくれる。トロに目がない真紀子の大好物だった。海苔の香りと鮪の脂がたまらない。子供がてらにこんなものを食べて贅沢だと思ったけど、これも寿司屋の娘の特権だと思っていた。
家を出てからはそんな事もなくなった。家を出たのと同時に寿司屋の娘の特権も失ったのだ。10年前に母の須磨子が他界し、1人で店を切り盛りしていた父親だったが癌を患ってから廃業していた。
社会人になり、それなりの給料を貰うようになって寿司屋に出入りもするようになったけど、父の巻いてくれたトロの手巻き以上に美味しいトロ鉄火に遭遇した事がなかった。
妹の貴和子に今週末、帰るとメールを返信して、クライアントとの打ち合わせを終えた帰り道、一軒の寿司屋を見つけた。
カウンターに座り、生ビールを頼んだ。真紀子より一回りぐらい歳上の大将に今日のおすすめを聞いた。
「今日はねぇ、塩釜からいい鮪が入ってるよ」
そう言って、嬉しそうに大将は冷蔵庫から鮪のブロックを取り出した。昔、父親の博もこんな風に嬉しそうに真紀子に見せてくれたものだ。まだ、掃除のしていない鮪のブロック。皮もまだ付いていた。もしかしたら、あの頃の皮ぎしの手巻きが食べられるかもしれない。
「大将、無理なお願いをしてもいいですか?その鮪の皮ぎしで手巻きを巻いて欲しいんです」
「お、旨いところ知ってんだねぇ。いいよ、お姉さん、べっぴんだしサービスしたげるよ」
大将はそう言って鮪を捌き出した。そして、皮ぎしの身をスプーンですくっている。真紀子の手にトロの手巻きが手渡された。
海苔の香りが鼻腔を擽る。頬張ると鮪の柔らかい脂の旨みが口の中に広がった。
あぁ、この味だ。子供の頃、お父さんが巻いてくれた手巻きの味。涙が出てきた。昔の思い出と一緒に。
「あ、ごめん、わさび入れすぎたかな」
真紀子は涙を拭きながら首を横に振った。

2017年6月22日 | カテゴリー:ブログ, 小さな寿司のストーリー |